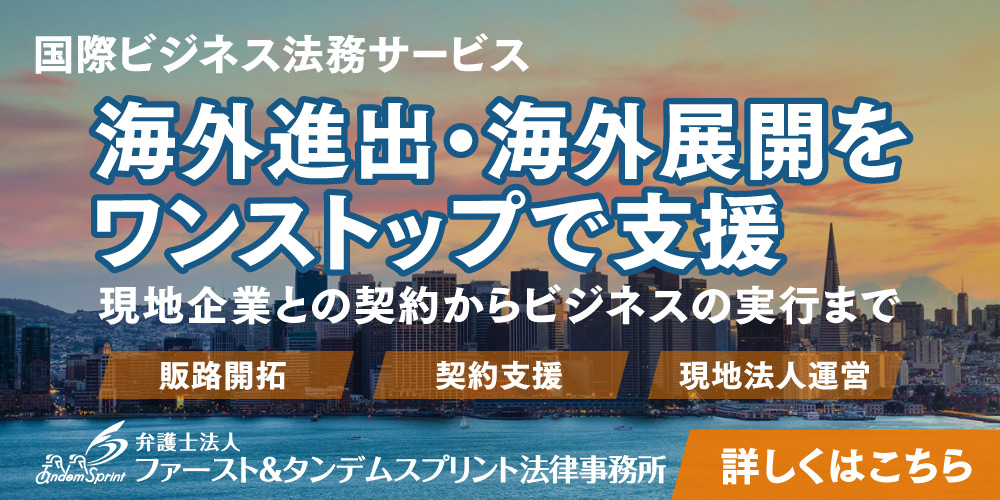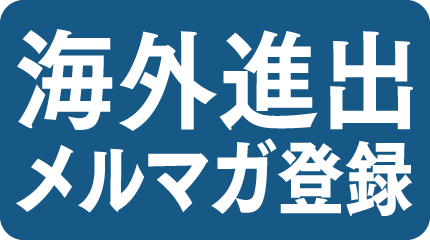1.はじめに

近年、アメリカのアパレル業界では、店舗数の削減や経営再建に踏み切るブランドや百貨店が増加しています。例えば、2019年にはバーニーズ ニューヨークやフォーエバー21が連邦破産法11条を申請しました。また、2020年春からは新型コロナウィルスの影響で、特に百貨店が経営難に直面しており、J.C.ペニー、ノードストローム、メイシーズなどが複数店舗の閉店を発表しています。
これに対し、Direct to Consumer(DtoC)という新しいビジネスモデルが、アメリカのアパレル業界で成長を見せています。このDtoCビジネスモデルは、製造者が直接消費者に製品を販売する形態であり、越境ECを活用することで、日本の企業にとっても魅力的な市場展開の手段となり得ます。
本稿では、アメリカのアパレル業界におけるDtoCスタートアップの事例を紹介するとともに、既存のビジネスモデルとDtoCの違い、および日本企業が越境ECを利用してアメリカ市場に進出する際のポイントについて詳しく解説していきます。
2.DtoCとは?

Direct to Consumer(DtoC)は、製造者が消費者に直接製品を販売するビジネスモデルを指します。このモデルでは、資金調達、設計、生産、販売、配送の全工程が同一企業によって管理されます。従来の小売ビジネスモデルと異なり、DtoCでは中間業者が介在しないため、生産者は消費者に直接製品を届けます。
特に注目されているのは、Digitally Native Vertical Brand(DNVB)と呼ばれるスタイルです。これは、インターネットに精通したミレニアル世代以下の消費者に焦点を当てたブランドで、Webを通じてストーリーテリングを用いて製品を販売します。このアプローチにより、ブランドは経費を削減し、高品質でデザイン性の高い製品を提供できるようになります。
越境ECの活用によって、DtoCモデルは国境を超え、グローバル市場への展開が容易になります。アパレルから食品業界に至るまで、さまざまな分野でこのモデルが採用されており、国際的な消費者基盤の獲得に貢献しています。このモデルは、日本企業にとっても、海外市場への進出戦略として有効な選択肢となり得るでしょう。
3.注目のDtoCブランド
2012年以降、ベンチャーキャピタルによるDtoCビジネスのスタートアップへの投資額は30億ドル以上にのぼります。ここでは、アメリカのアパレル界で注目のDtoCスタートアップをいくつか紹介します。
Warby Parker(ワービー・パーカー)
https://www.warbyparker.com/
Warby Parkerは、2010年にペンシルバニア大学に在学中であった4人の学生が立ち上げたメガネのDtoCブランドです。Warby ParkerのDtoCモデルでは、まず顧客に複数種類のメガネを送付します。そして、顧客は自宅で試着後、不要なメガネを送り返すのです。顧客が店舗に足を運ぶことなくオンラインで試着、購入できる仕組みが、Warby Parkerの特徴で、自宅で眼鏡を選ぶ便利さが受けて、創業以降大きな成長を見せています。
Warby Parkerでは、顧客が眼鏡の試着写真をSNS上に投稿して、友人や家族にアドバイスを求めていることをうまくマーケティングに活用しています。#warbyhometryonのハッシュタグでSNSに試着画像を投稿するよう顧客に依頼しています。そして、その見返りとして、顧客はオンラインのパーソナルスタイリストからアドバイスを受けることができるのです。また、同社ではインフルエンサーマーケティングにも積極的です。YouTubeのインフルエンサーに、メガネを提供、試着動画を投稿してもらっています。
Everlane(エヴァーレーン)
https://www.everlane.com/
2010年に創業したEverlaneは、それまでのアパレル業界では前例のないコンセプトを備えていました。各製品の製造にかかる費用について全内訳(原価・材料費・労働費・関税・輸送費・工場リストなど)を公開しています。また、Everlaneのウェブサイトでは、製品が製造されている工場を垣間見ることができ、衣服を作っている労働者の様子を見ることができます。主にミレニアル世代の消費者層を中心に過剰なまでの透明性が支持を得て、Everlaneは飛躍的に成長しました。
2018年、Everlaneはサプライチェーンからバージンプラスチックを排除し、オフィスおよびサプライチェーン全体で使い捨てプラスチックの使用をやめるという野心的なプロジェクトに着手しました。そのプロジェクトの一環として、リサイクルされたペットボトルを原材料としたアウターウェアを開発し、コレクション内のすべてのアイテムについて、リサイクルされたプラスチックで作っているとのことです。
Dollar Shave Club(ダラーシェイブクラブ)
https://www.dollarshaveclub.com/
2011年設立のDollar Shave ClubではサブスクリプションベースのDtoCビジネスモデルをとっています。サービスに登録すると、毎月自動課金され、毎月、商品(カミソリの替刃)が顧客の家に直接送られます。
驚くべきはわずか1ドルという低価格です。Dollar Shave Clubは高性能・高品質の流れに逆行して、シンプルで最低限の機能性の製品を作ることで製造コストを最小限に抑えたのです。また、DtoCモデルなので、仲介業者にかかるコストを省くことができます。このように他の製品に比較して圧倒的な低価格を実現することで、市場シェアの獲得に成功しました。
Dollar Shave Clubの顧客数は2016年には300万人に達し、同年Unileverに10億ドル(約1140億円)で買収されました。設立時の資金調達総額は1億6300万ドル(約185億円)だったので、設立から年で大きな成長を遂げたことが分かります。
Casper(キャスパー)
https://casper.com/
Casperは、2014年に設立されたマットレスブランドのDtoC企業です。ベッドの利用が一般的なアメリカでは、日本に比べるとマットレス市場は非常に大きなものです。
マットレスの購入では、ソフト、プラッシュ、セミファーム、ファームといった硬さをはじめとして、価格、サイズ、素材など様々な選択肢を検討する必要があります。Casperでは、マットレスの完成度を高め、選択肢を極限に減らすことで、ユーザーの選ぶストレスを低減させたことがヒットに繋がりました。また、100日間の返品保証や、自宅までの配送など、消費者に安心感と利便性をもたらしていることが受け入れられています。
Casperでも、インフルエンサーマーケティングを行なっています。そして、ターゲット層を広く持つのではなく、都市部に住むミレニアル世代の消費者層にリーチする戦略をとっています。トレンディでユニークなブランドイメージを掲げ、従来のマットレス企業との差別化を図っています。
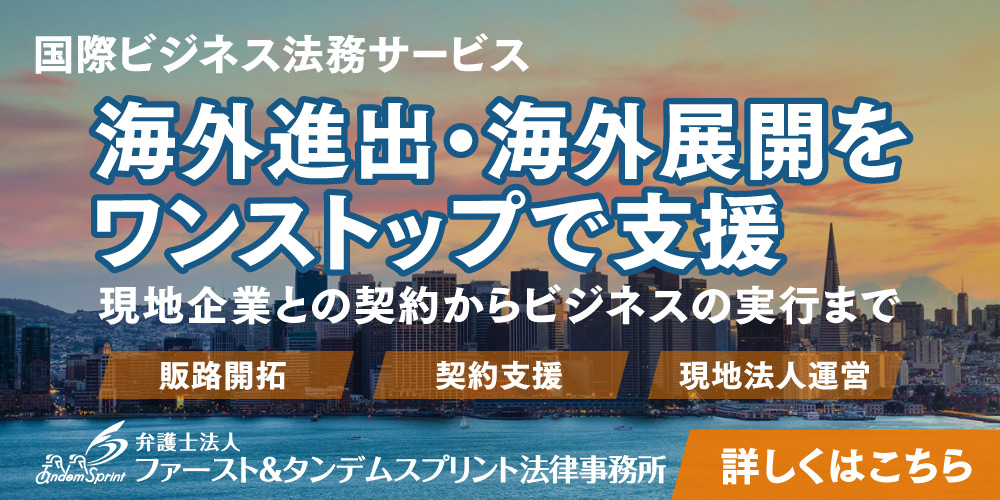
4.なぜDtoCが増えてきたのか?

ここ数年で、DtoCが成長を見せているのには、いくつかの理由が考えられます。ここではDtoCを後押しする要因について考察します。
・ソーシャルメディアによる消費者への容易なアクセス
インフルエンサーマーケティングの台頭、特にInstagramを通じた露出は、新たなブランドでも低コストで幅広い消費者層にリーチすることを可能にしています。これにより、越境EC市場においても、国際的な顧客基盤の構築が容易になっています。
・インフラストラクチャ
AWSやGoogle Cloudといったクラウドプラットフォームの発展は、スケーラブルなビジネスモデルの構築を容易にしています。また、StripeやShopifyなどのサービスは、ECビジネスを効率的に実行するための強力な基盤を提供しています。これらの進化したインフラは、特に越境ECにおいて有利な環境を提供します。
・プロトタイピングのスピード
中国との商業チャネルが活発化したことで、アメリカのスタートアップは中国の製造リソースを活用して迅速にプロトタイプを作成できるようになりました。これにより、新しい製品を素早く市場に投入し、越境EC市場でのビジネス展開がスムーズに行えるようになっています。
・クラウドファンディングの活用
IndiegogoやKickstarterのようなクラウドファンディングサイトは、スタートアップにとって早期の需要を生み出す重要なプラットフォームを提供しています。これらのプラットフォームは、資金調達だけでなく、製品の市場性をテストする手段としても役立っています。越境ECにおける新規事業や製品の市場導入において、これらのサイトは貴重な資源となり得ます。
5.日本のDtoCビジネス
海外で盛り上がっているアパレル界のDtoCですが、徐々に日本国内でもDtoCブランドが広がってきています。ここでは、日本のアパレルDtoC企業を紹介します。
Factelier
https://factelier.com/
「職人の情熱とこだわりがつまった語れる商品を適正価格で」というブランドコンセプトのもと、工場直結アパレルブランドを展開しています。中間業者を介さず工場と消費者を直接結ぶことで、工場独自のこだわりを詰め込んだ高品質な商品を、従来の1/2以下の価格で提供できるとしています。
MIXX
https://mixx.jp/
「わたしらしいを選ぼう」というブランドコンセプトのもと、質問に答えていくだけで自分だけにカスタマイズされたシャンプーをオーダーメイドすることができるサービスを提供しています。
picki
https://picki.jp/
pickiはある特定のブランドを提供しているのではなく、アパレル界のDtoCプラットフォームを展開しています。クリエイターがオリジナルのアパレルブランドを立ち上げることができる新たな仕組みです。『7割のサンプル』を作るというコンセプトを掲げ、消費者が一緒にものづくりに参加できる余白を残していることが特徴です。
6.越境ECにおけるDtoCブランド展開の戦略と機会

越境ECにおけるアパレル業界で注目されているのは、製造小売(SPA)スタイルのDtoCビジネスモデルです。このモデルで成功するためには、企業とユーザー間の強固な関係構築が鍵です。DtoCの直接販売の特性を活かして、ユーザーがブランドとの一体感を感じられるコンテンツを提供することで、従来の小売ビジネスでは得られなかった付加価値を創出できます。
インターネットの普及により、オンラインで消費者に直接アピールするアパレルブランドを立ち上げるハードルが低くなり、特に海外市場でのDtoCビジネスの拡大が見られます。このため、日本企業が海外でDtoCブランドを展開することは大きなメリットをもたらします。
消費者は汎用的な大量生産ブランドよりも、ブランドのメッセージに共感し、自身もブランドの一員であるという感覚を求めています。このような購買文化の変化は、新しいビジネスモデルの誕生に強く寄与しています。
日本企業が海外で実店舗を開設するのは困難ですが、オンラインショップであれば既存のプラットフォームを活用し、越境ECにおける進出のハードルを下げることが可能です。オンラインでの成功の後、実店舗の開設を検討することも可能になります。
DtoCでは中間業者を省くことで、顧客のニーズを直接捉えることが容易になり、海外進出時のビジネス文化の違いに対する悩みが軽減されます。アパレル業界で海外進出を目指す日本企業にとって、アメリカのDtoCスタートアップの動向は多くの示唆を与えるでしょう。