目次
1.はじめに

現在、米国では様々なサービスで「グッド、ベター、ベストプライシング」と呼ばれる段階的な価格設定が設けられています。これは、顧客に対して3つ以上のサービスレベルを提示し、それぞれのサービスレベルに応じて価値と価格を増加させる価格戦略のことです。例えば、「ブロンズ→シルバー→ゴールド」あるいは「ベーシック→アドバンス→デラックス」などのパッケージを設けます。パッケージの価格は段階的に高く設定されていますが、その分、追加サービスやアップセルなどが含まれるのです。
「グッド、ベター、ベストプライシング」により、企業側はさまざまな顧客のニーズと予算に最適なパッケージまたはサービスを提供することができます。幅広いターゲットオーディエンスにアピールすることにもつながり、現在、サブスクリプションサービスやオンラインサービスを提供する業界を中心に、「グッド、ベター、ベストプライシング」モデルの活用が広がっています。
本稿では「グッド、ベター、ベストプライシング」メリットを詳しく説明するとともに、本価格戦略によって成功している米国企業の事例も紹介します。
商品やサービスの価格戦略はビジネスにおいて非常に重要な要素となります。そのため、海外展開の際には、現地の競合他社の価格設定を参考にすることも多いと思います。今回紹介する「グッド、ベター、ベストプライシング」は、海外市場で適切な価格設定とする上でも、有効となります。海外企業の実際のサクセス事例を参考にして、海外進出の成功へとつなげていただけますと幸いです。
2.「グッド、ベター、ベストプライシング」のメリット
2−1.製品をより手の届きやすいものにする

グッド、ベター、ベストの段階的な価格設定により、製品・サービスは顧客にとってより手の届きやすいものとなります。手頃感のある価格を最低モデル「グッド」として使用して、まずは新規顧客を呼び込むのです。新規顧客を獲得した後は、顧客に良い商品体験を感じてもらい、「グッド」から「ベター」や「ベスト」という高次元のプランにリピーターとして戻ってきてもらうことも期待できます。
手頃な価格プランを用意しておくことで、新規顧客が製品・サービスを試してみようと考えるまでのハードルを下げることにつながります。海外市場に新規参入を考えている日本企業にとって、このメリットは非常に有益になるのです。
2−2.利益率とブランド価値の向上
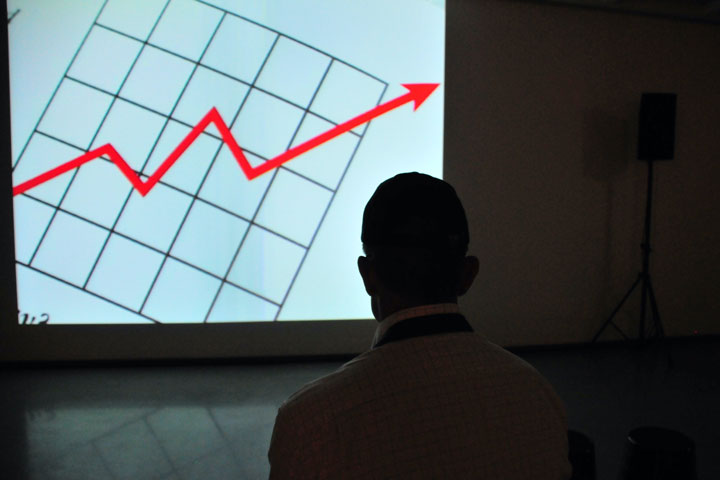
「グッド、ベター、ベストプライシング」では、段階的な価格設定のハイエンドプランで利益率を上げることもできます。「グッド」で新規顧客を獲得しつつ、「ベスト」の顧客層を増やしていくことで、利益率を高めるのです。また、ハイエンドのプランで提供するプレミアムな体験は、顧客に特別感を感じさせ、ポジティブなハロー効果によってブランドの価値を引き上げることにもなります。
2−3.さまざまなタイプの顧客にアピール

潜在顧客の中には様々な感度の顧客がいます。企業側がある程度のターゲット層を定めているとしても、それぞれの潜在顧客が求めている機能性や価格設定は異なるのです。複数の選択肢を提供することで、顧客自身で自分にとって最適なものを選択できるようになります。
2−4.消費者心理を企業にとって都合の良い方向に動かす

「グッド、ベター、ベストプライシング」では、以下3つの理由から、企業にとってプラスとなる方向へ消費者心理を動かすことが可能と考えられています。
1つ目は、製品・サービスラインを理解しやすくなる点です。つまり、段階的な価格設定を使用することで、製品の様々な機能が分解した状態で可視化されます。潜在的な顧客が製品・サービスを正確に理解し、自分にとって必要な機能を判断することが容易になります。
2つ目は、より高い価格そのものが顧客の購買意欲の高める可能性があるという点です。様々な書籍を執筆しているウィリアム・パウンドストーン氏による一冊 『プライスレス 必ず得する行動経済学の法則(原題Priceless:The Mith of Fair Value And How to Take Advantage of It)』の中で紹介された興味深い実験を紹介しましょう。
実験で「高価格のプレミアムビールA」と「低価格のバーゲンビールB」を提示したところ、約80%の人が高価なプレミアムビールAを選びました。次に「より低価格のスーパーバーゲンビールC」を加えると(A>B>C)、今度は約80%がビールBを買い、残りの人がビールAを買い、最低価格のビールCを買う人はいませんでした。追加するビールを安いものではなく、最高額のスーパープレミアムビールD(D>A>B)にすると、ほとんどの人がビールAを選び、少数の人がビールBを選び、約10%の人がビールDを選んだそうです。
この実験からは、常に最も高価な商品を選ぶ割合が一定数あること、そして選択肢が3つに増えると、真ん中の価格のオプションを選択する割合が高くなることが示されています。そのため、単一の価格設定にするよりは、「グッド、ベター、ベストプライシング」の方が利益が大きくなるといえます。そして、最も売りたい商品やサービスプランは3つの価格帯の中で中間のもの「ベター」にすると良いと考えられます。
3つ目は、複数の価格帯を提案することで、潜在顧客に「買う」と「買わない」ことを考えさせるのではなく、売っている中からどれを買うかという気持ちへと変化しやすいという点です。つまり、購入を前提として、3プランの中でどれが一番お得かという消費者心理になるので、購入に至る割合が高くなると期待できます。
3.米国企業の「グッド、ベター、ベストプライシング」事例
3−1.米アマゾンのオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」
(https://www.audible.com)
通販サイトAmazonが運営するオーディオブックサービス、Audible(オーディブル)では、米国エリアで以下3段階の価格設定を展開しています。
グッド:Audible Plus
月額7.9ドルで11,000を超える無料タイトルカタログへの無限アクセス
ベター:Audible PremiumPlus
月額14.95ドルで、無料タイトルへの無限アクセスに無料タイトル以外のコンテンツをダウンロードするためのクレジットを毎月1つ取得
ベスト:Audible Premium Plus – 2 credits
月額22.95ドルで、無料タイトルへの無限アクセスに無料タイトル以外のコンテンツをダウンロードするためのクレジットを毎月2つ取得
3−2.SNS用の管理プラットフォームを提供する「Sprout Social(スプラウト・ソーシャル)」
(http://sproutsocial.com/)
2010年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置くSprout Social(スプラウト・ソーシャル)は、ソーシャルメディア(SNS)管理プラットフォーム企業です。現在、企業にとってSNSはマーケティング効果の大きいプラットフォームであり、SNSマーケティングの重要性が増しています。一方で、複数のSNSを活用するのは簡単ではありません。
スプラウト・ソーシャルが提供する管理プラットフォームでは複数のSNSを統合するとともに、自動化機能を搭載してSNS運用の負担を軽減してくれます。
スプラウト・ソーシャルでは、3つの異なるプランを提供しており、高価格のプランになるほど複雑な管理が可能となっています。
グッド:Standard
月額99ドル
アカウント上限:5
基本的な管理・レポート機能
ベター:Professional
月額169ドル
アカウント上限:10
複雑な管理・レポート機能
ベスト:Advanced
月額279ドル
アカウント上限:10
複雑な管理・レポート機能および自動化ツール
3−3.経理プラットフォームを提供する「Pilot(パイロット)」
(https://pilot.com/)
2016年にカリフォルニア州サンフランシスコで設立されたPilot(パイロット)は、経理、税務、CFOサービスを提供するプラットフォーム企業です。従来型の外部委託サービスに比較して、時間、コスト、および労力を削減できるとして、成長段階にあるスタートアップ企業から受け入れられています。
Pilotの経理ツールでは、企業のプランに応じて以下3つの異なるプランを提供しています。
グッド:Core
月額599ドル
企業直後のスモールビジネス向け
ベター:Select
月額849ドル
成長を加速したい(ビジネス規模を拡大したい)企業向け
ベスト:Plus
月額カスタマイズ価格
規模の大きな企業向け
4.海外進出・海外展開への影響
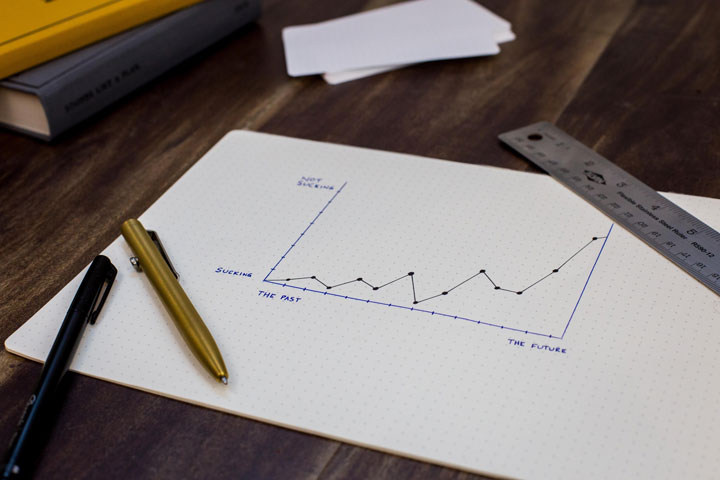
業界に関わらず、製品やサービスの価格戦略は、ビジネス成功にとって鍵となる重要な要素です。同じサービス、価格だとしても、見せ方によってはより魅力的に見えることもあります。消費者心理に効果的に働きかける価格戦略として米国企業では「グッド、ベター、ベストプライシング」の採用が一般的です。本稿で紹介した企業のサービスプライシングにおける取り組みに限らず、小売店の広告など様々な場面に応用されています。
日本企業が海外進出する際には、価格戦略の1つとして「グッド、ベター、ベストプライシング」の導入を考えてみてはいかがでしょうか。自社サービスをわかりやすく紹介するとともに、他社との比較ではなく、自社内でのプラン内比較という思考に消費者を導くため、顧客獲得に有効です。また、低価格帯で顧客を獲得した後に、高価格帯のプランで収益性を高める段階にも移行しやすくなります。











