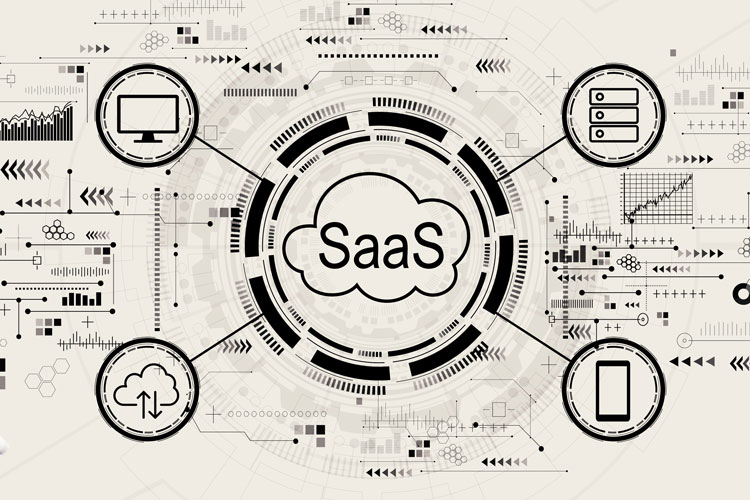目次
1.はじめに

現在、企業の規模・業界を問わず、クラウドコンピューティングサービスの活用が常識となっています。クラウドコンピューティングサービスの最大の特徴は、その弾力性で、企業の必要性に応じて、サイズを自由自在に変更できます。
従来のITでは、企業はIT資産(ハードウェア、システムソフトウェア、開発ツール、アプリケーションなど)を購入し、インストールし、管理し、自社のオンプレミスデータセンターで維持する必要がありました。一方、クラウドコンピューティングサービスでは、クラウドサービスプロバイダーが資産を所有、管理、維持してくれるため、顧客はインターネット接続を介して資産を消費し、その対価を定額制または従量制で支払うこととなります。
特に、資金や人材が潤沢ではない創業期のスタートアップ企業や、海外進出・海外展開などで新しい市場を開拓する時期の企業は、初期コストは抑えつつ、規模を拡大していく状況にあります。そのため、必要に応じて実行・停止ができ、使った時間に応じて対価を支払うクラウドコンピューティングサービスモデルとの相性は、非常に良いといえます。
最も一般的な3つのクラウドコンピューティングサービスモデルとして、「Saas」「Iaas」「Paas」があります。
● SaaS(Software as a Service)とは、クラウド上でホストされる、すぐに使えるアプリケーション・ソフトウェアをオンデマンドで利用できるサービスです。
● IaaS(Infrastructure as a Service)は、クラウド上でホストされる物理サーバーや仮想サーバー、ストレージ、ネットワークをオンデマンドアクセスで利用できるサービスを指します。クラウド上でアプリケーションやワークロードを実行するためのバックエンドITインフラストラクチャともいえます。
● PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーションの開発、実行、保守、管理を行うための、クラウドホスティングされた完全ですぐに使えるプラットフォームをオンデマンドアクセスで利用できるサービスを意味します。
SaaS、IaaS、PaaSは相互に排他的なものではありません。多くの企業が複数のものを利用しています。
本稿では、SaaS、IaaS、PaaSのメリットや応用事例について説明するとともに、それらをどのように組み合わせることができるのかを紹介します。
2.SaaSとは

SaaSとは、クラウドホスティングされた、すぐに使えるアプリケーションソフトウェアのことです。ユーザーは、アプリケーションを使用するために、月額または年会費を支払います。Webブラウザ、デスクトップアプリ、またはモバイルアプリの形式があり、それらを利用するために必要なすべてのインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア、データストレージなど)は、SaaSベンダーによってホストおよび管理されています。
SaaSの最大のメリットは、インフラとアプリケーションの管理を、すべてSaaSベンダーに肩代わりしてもらえることです。ユーザーは、アカウントを作成し、料金を支払って、アプリケーションを使い始めるだけでよく、サーバーのハードウェアやソフトウェアのメンテナンスから、ユーザーアクセスやセキュリティの管理、データの保存と管理、アップグレードやパッチの適用など、その他のことはすべてベンダーが行ってくれます。
その他にも、SaaSの利点は複数あります。
● リスクを最小限に抑える:多くのSaaS製品では、無料試用期間や低額の月額費用を設定しています。ユーザーは経済的なリスクをほとんど負うことなく、ソフトウェアを試用してニーズを満たすかどうかを確認することができます。
● いつでも、どこでも利用可能:ブラウザとインターネット接続があれば、どんなデバイスでもSaaSアプリケーションを利用することができます。
● スケーラビリティ:追加料金を払うだけで、ユーザーやデータを追加する事が可能です。
現在、あらゆる個人向けアプリケーションや従業員向け生産性アプリケーションがSaaSとして提供されており、具体的なユースケースは数え切れないほどあります。スマートフォンを持っている人であれば、ほぼ間違いなく何らかの形でSaaSを利用しているともいえます。
電子メール、ソーシャルメディア、クラウド・ファイル・ストレージ・ソリューション(DropboxやBoxなど)は、人々が個人生活で日常的に使っているSaaSアプリケーションの一例です。
ビジネスや企業向けのSaaSとしては、Salesforce(顧客関係管理ソフトウェア)、HubSpot(マーケティングソフトウェア)、Trello(ワークフロー管理)、Slack(コラボレーションとメッセージング)、Canva(グラフィック)などがよく知られています。
また、Adobe Creative Suiteのようなデスクトップ向けのアプリケーションも、Adobe Creative CloudのようなSaaSとして提供されています。
エンドユーザーや企業は、必要な機能を備えたSaaSソリューションを選択することで、オンプレミスのソフトウェアに代わる、よりシンプルで拡張性の高い、よりコスト効率の高いサービスを利用できるようになります。
3.IaaSとは

IaaSは、クラウドホスティングによるコンピューティングインフラ(サーバー、ストレージ容量、ネットワークリソースなど)をオンデマンドアクセスで利用できるサービスのことです。ユーザーは、オンプレミスのハードウェアとほぼ同じ方法で調達、設定、使用することができます。
IaaSのユーザーは、インターネット接続を介してハードウェアを使用し、その使用料をサブスクリプションまたは従量課金で支払います。一方、ベンダー側は、自社のデータセンターでハードウェアとコンピューティングリソースをホスト、管理、保守していきます。
IaaSは、「As a Service」の原型ともいえます。Amazon Web Services、Google Cloud、IBM Cloud、Microsoft Azureなど、主要なクラウドサービスプロバイダーはいずれも、何らかの形でIaaSを提供することから事業をスタートさせました。
IaaSの最大のメリットは、その柔軟性と初期投資の抑制です。IaaSを利用することで、ユーザーは自社でオンプレミスデータセンターを購入・維持するための初期費用を回避することができます。また、トラフィックの急増や減速に対応するのも簡単です。
IaaSのその他の利点は、以下のとおりです。
● 可用性の向上:IaaSでは、冗長化されたサーバーを簡単に作成することができます。また、他の地域にもサーバーを作成し、地域の停電や物理的な災害の際にも可用性を確保することができます。
● 低レイテンシーとパフォーマンスの向上:IaaSプロバイダーは通常、複数の地域でデータセンターを運営しています。ユーザーに近い拠点を選択することで、レイテンシーを最小限に抑え、パフォーマンスを最大化することができます。
● 応答性の向上:ユーザーは数分で設定利用開始することができます。そのおかげで新しいアイデアを迅速にテストし、展開することが可能です。
● 包括的なセキュリティ:オンサイト、データセンター、および暗号化による高水準のセキュリティにより、クラウド・インフラを社内でホストしたのと同等以上の高度なセキュリティと保護を利用することができます。
● 最高水準のテクノロジー:クラウドプロバイダーは、次サービスの競争力向上のため、最新のテクノロジーをユーザーに提供しています。ユーザーは、それらのテクノロジーを、オンプレミスで実装するよりもはるかに早く(そしてはるかに少ないコストで)利用することができます。
IaaSの一般的な用途は、以下の通りです。
● ディザスタリカバリ:既存インフラにディザスタリカバリ・ソリューション(地震や津波などの災害によってシステムの継続利用が不可能になった際の復旧および修復、あるいはそのためのシステム)を展開することができます。
● Eコマース: IaaSは、トラフィックが頻繁に急増するオンライン小売業者にとって優れた選択肢となります。小売業界では、需要の多い時期にスケールアップできる能力と、高品質のセキュリティが不可欠となるためです。
● モノのインターネット(IoT)、イベント処理、人工知能(AI):大量のデータを扱うアプリケーションのデータストレージやコンピューティングリソースのセットアップとスケールアップが可能です。
● スタートアップ企業や新規市場開拓:スタートアップ企業や海外展開の初期には、オンプレミスのITインフラに資本を投下する余裕がありません。IaaSを利用すれば、ハードウェアへの先行投資や管理に伴う間接業務なしに、エンタープライズレベルのデータセンター機能を利用できます。
● ソフトウェア開発: IaaSは、テストや開発環境のインフラをオンプレミスよりも迅速に構築することができます(ただし、このユースケースは、次のセクションで説明するように、PaaSの方が適していることが多いです。)。
4.PaaSとは
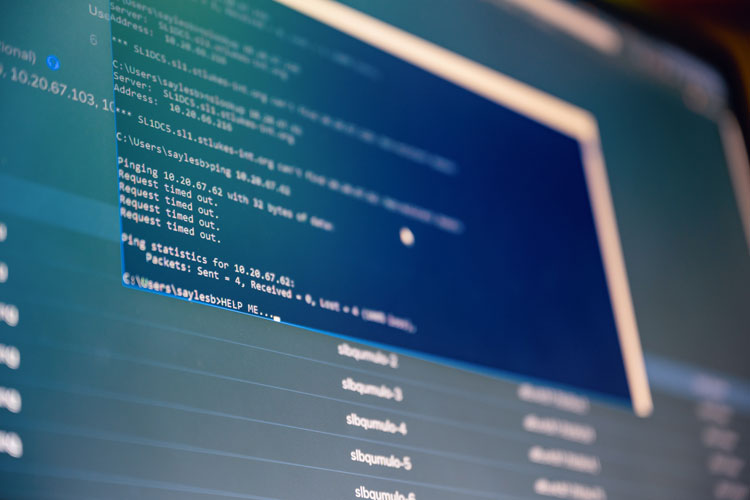
PaaSは、アプリケーションを開発、実行、管理するためのクラウドベースのプラットフォームを提供します。 ユーザーは、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を通じてPaaSにアクセスし、開発チームやDevOpsチームは、コーディング、統合、テスト、配信、配備、フィードバックなど、アプリケーションライフサイクル全体にわたってすべての作業を共同で行うことができます。
PaaSソリューションの例としては、AWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、Microsoft Windows Azure、Red Hat OpenShift on IBM Cloudなどが挙げられます。
PaaSの主な利点は、ユーザーが独自にオンプレミスプラットフォームを構築・管理する場合よりも、より迅速かつコスト効率よくアプリケーションを構築、テスト、デプロイ、実行、更新、拡張できるようになることにあります。
また、以下のようなメリットもあります。
● 市場投入までの時間を短縮:PaaSを利用することで、開発チームは開発、テスト、本番の各環境を、数週間から数カ月かけることなく、数分で立ち上げることができます。
● 新技術を低リスクでテストし、採用できる:PaaSプラットフォームでは、通常、アプリケーションスタックの上下にある最新のリソースに幅広くアクセスすることができます。これにより、企業は新しいオペレーティングシステムや言語、その他のツールを、それらに対する多額の投資や、それらを実行するために必要なインフラストラクチャへの投資を行うことなく、テストすることができます。
● コラボレーションの簡素化:クラウドベースのサービスであるおかげで、PaaSでは、インターネット接続さえあれば、開発チームと運用チームはどこからでも必要なツールにアクセスすることができます。
● よりスケーラブルなアプローチ:PaaSでは、アプリケーションの構築、テスト、ステージング、実行に必要な容量をいつでも追加購入することができます。
● 管理の手間を軽減:PaaSでは、インフラストラクチャの管理、パッチ、アップデートなどの管理作業をクラウドサービスプロバイダーに委託することができます。
PaaSは、以下のようなプロジェクトに最適です。
● APIの開発と管理:PaaSにはフレームワークが組み込まれており、アプリケーション間でデータや機能を共有するためのAPIの開発、実行、管理、保護を簡単に行うことができます。
● モノのインターネット(IoT): PaaSは、IoTアプリケーションの開発やIoTデバイスからのデータのリアルタイム処理に使用されるさまざまなプログラミング言語(Java、Python、Swiftなど)、ツール、アプリケーション環境をサポートしています。
● アジャイル開発とDevOps:PaaSソリューションは、通常、DevOpsツールチェーンのすべての要件をカバーしています。さらに、継続的インテグレーションと継続的デリバリー(CI/CD)をサポートするためのビルトイン自動化も提供します。
● クラウドネイティブ開発とハイブリッドクラウド戦略:PaaSソリューションは、マイクロサービス、コンテナ、Kubernetes、サーバーレスコンピューティングなどのクラウドネイティブな開発技術をサポートしており、開発者は一度構築すれば、プライベートクラウド、パブリッククラウド、オンプレミス環境にわたって一貫したデプロイと管理を行うことができます。
5.海外進出・海外展開への影響

ビジネスの計画を前進させ、目標を達成するためには、支出の無駄を抑え、キャッシュフローを把握することが必要不可欠です。
特に、システム導入時には、「導入時の初期コスト」と「運用時のランニングコスト」が関わってくるため、見積もりを取るなどして、性能とコスト面を満たしたサービスを見つけることが重要です。。
旧来の自社運用型(オンプレミス型)の場合は、自社内にサーバーを置きシステムを管理するため、サーバー本体の購入費用に加えて、設定に関する人件費、必要なOSやソフトウェアの費用などを導入時に準備する必要があります。そのため初期投資は大きくなりがちです。また、ランニングコストとして、維持メンテナンス費用や障害時の復旧対応、バージョンアップ時にかかるコストなども見込んでおく必要があります。
一方、今回紹介したクラウド型のAs-a-Serviceの場合は、初期費用が無料あるいは格安なことが多く、定額や従量課金という形でランニングコストを支払うことになります。また、バージョンアップやメンテナンスは、サービス提供会社が行うため、自社での負担を抑えるとともに、将来的な支出も予測しやすいといえます。
このようなメリットから、現在では、ほとんどの企業は複数の「As-a-Service」を利用しています。ただし、重要なことは、必要とする機能、および自社のスタッフが持つ専門知識を考慮して、適切なAs-a-Serviceソリューションを選択することです。例えば、リモートサーバーを設定・運用するためのIT専門知識が社内にない場合、IaaSはあまり適していませんし、開発チームがない場合、PaaSは必要ありません。
海外進出・海外展開を行う際にも、本稿で紹介した各As-a-Serviceの特徴を理解し、うまく活用して、限られたキャッシュフローの中で事業を拡大を目指していくと良いでしょう。